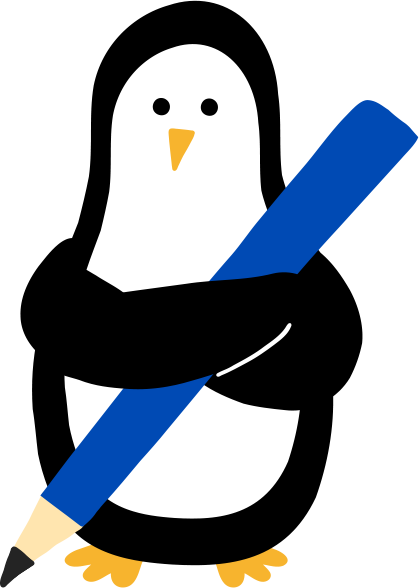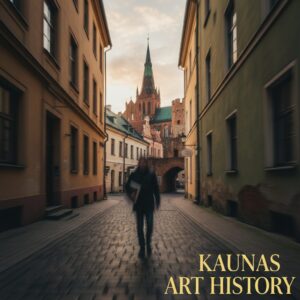ヨーロッパの空の下、僕はいくつもの街の石畳を踏みしめてきた。パリのシャンゼリゼ、ローマのフォロ・ロマーノ、プラハのカレル橋。どれもがそれぞれの歴史をその凹凸に刻み込み、旅人の足音に静かに応えてくれる。けれど、アルバニア南部、ドリーナ渓谷を見下ろす山肌に張り付くように存在する街、ジロカストラの石畳ほど、僕の心に深く、そして静かに語りかけてきた道はなかったかもしれない。
「石の街」あるいは「銀の城」。その異名は伊達じゃない。陽の光を浴びて鈍く輝く石灰岩の屋根は、まるで巨大な竜の鱗のようだ。坂道を登るたびに息が切れるけれど、ふと振り返れば、重なり合う石の家々と、その向こうに広がる雄大な山々の景色が、すべての疲れを忘れさせてくれる。ここは、ただ美しいだけの観光地ではない。オスマン帝国時代の面影を色濃く残すこの街の石の一つひとつに、人々の営みの記憶が、そして何世代にもわたって受け継がれてきた物語が、深く染み込んでいる。
そんなジロカストラで僕が探し求めたのは、壮大な城塞でも、歴史的な博物館でもなかった。僕が本当に触れたかったのは、この石の街の心臓部、日々の暮らしの中に息づく温かい何か。そう、それは「食」という形で僕を待っていてくれた。オスマンの時代から続く伝統的な調理法で、地元の食材を使い、家族のために作られてきた素朴な家庭料理。その一皿にこそ、ジロカストラの真の魂が宿っていると、僕の旅の勘が告げていた。これから綴るのは、僕がジロカストラの家庭のキッチンで出会った、忘れがたい味と、人の温もりの物語だ。
ヨーロッパの秘境をさらに探求したい方は、フェロー諸島ガサダール村の断崖と発酵文化の旅もご覧ください。
迷宮のような街で歴史の音を聴く

ジロカストラに到着してから最初の数日間、僕は特に目的もなく、ひたすら歩き続けていた。迷路のように入り組んだ石畳の坂道は、時に急な斜面となり旅人の体力を削るものの、その先で現れる風景が何よりのご褒美となった。頭上に迫る石造りの屋根や、蔦の絡まる壁、木製のバルコニーからこぼれる人々の話し声。どこを切り取ってもまるで一枚の絵葉書のような風景だった。
街の中心部に位置する旧バザールは、今もなお人々の暮らしの拠点として賑わいを見せている。石のアーチが連なる通りには、土産物店やカフェ、さらに絨毯や銀細工を手掛ける職人の工房が軒を連ねていた。金属を打つカラン、コロンという音が響きわたり、カフェからは濃厚なトルココーヒーの香りが漂う。店先で交わされる明るい挨拶の数々。それらが入り混じり、ジロカストラの日常という名の交響曲を奏でていた。音楽大学を中退した僕の耳には、その不協和音さえも心地良く響いた。
この街の歴史は実に複雑である。古代ギリシャ時代から人々が住み続け、ビザンツ帝国を経て、500年近くにわたりオスマン帝国の支配下に置かれ、やがて近代アルバニアの礎が築かれた。街の頂にそびえるジロカステル城は、長きにわたる支配者の移り変わりを静かに見守ってきた歴史の証人だ。城壁に立てば、眼下に広がる石造りの屋根の波や、ドリーナ川が潤す緑豊かな渓谷を一望できる。吹き抜ける風の中に、かつてこの地で繰り広げられたであろう戦いの叫びやバザールの喧騒が混ざり合って聞こえてくるような気がした。
さらにこの街は、アルバニアの独裁者エンヴェル・ホッジャの生誕地としても知られている。彼の時代にジロカストラは「博物館都市」として、その古い街並みが厳しく保護された。皮肉にも、彼の独裁政治こそがこの類稀なる景観を現代にまで残す一因となったのだ。街を歩いていると、歴史の光と影が石畳の模様のように複雑に絡み合っていることを身に染みて感じる。それは単なる美しさを超えた、深みと重みのある街の魅力そのものだった。
旅の心を温める、ジロカストラの素朴な宝物
街の空気に徐々に馴染んでいくと、自然と僕の関心は「食」へと向かっていった。レストランのメニューをじっくり見たり、市場に並ぶ野菜をよく観察したり、地元の人々が何を食べているのかを注意深く見届けたりした。ジロカストラには、この地独自の、何世代にもわたって愛され続けてきた料理が数多く存在することにすぐに気がついた。
まず僕を虜にしたのは、「Qifqi(キフチ)」という小さなライスボールだった。炊いた米に卵、細かく刻んだミント、塩胡椒を混ぜ合わせて丸め、特別な鉄鍋で焼き上げるか、油で揚げるシンプルな一品だ。旧バザールにある小さな食堂で初めて味わったときの感動は、いまでも鮮明に覚えている。外はカリッと香ばしく、中はふんわり柔らかい。噛むたびにミントの爽やかな香りが鼻を抜け、米の穏やかな甘みと卵のコクが口いっぱいに広がった。まるでジロカストラの太陽をぎゅっと閉じ込めたかのような、素朴で力強い味わいだ。軽食として手軽に楽しめることもあって、街歩きの合間に何度もキフチを頬張った。
次に、アルバニア全土で親しまれている国民食「Tavë Kosi(タヴァ・コシ)」も、ジロカストラで味わうとひと味違った。これはラム肉をヨーグルトと卵、米などを混ぜたソースで包み込み、土鍋でじっくりオーブン焼きにした料理だ。レストランで注文すると、熱々の土鍋がグツグツと音を立てながら運ばれてくる。スプーンを入れると、こんがり焼けた表面の下からチーズのように濃厚でクリーミーなソースと、びっくりするほど柔らかく煮込まれたラム肉が姿を見せる。ヨーグルトのほどよい酸味がラムのクセを和らげ、全体の味を見事にまとめ上げている。これはもはや贅沢なご馳走だ。旅の疲れを一気に吹き飛ばすような、心身に染みわたる一皿だった。
さらに、僕のお気に入りの一品に加わったのが「Pasha Qofte(パシャ・チョフテ)」というスープだ。ふんわりとしたミートボールが、レモンと卵でとろみをつけた優しい酸味のスープに浮かんでいる料理である。見た目はとてもシンプルだが、一口飲めばその深い味わいに驚かされる。ミートボールの肉汁が溶け出したスープはどこか懐かしく、まるでおばあちゃんが作る家庭の味のような温もりに満ちている。少し肌寒い夜にこのスープをすすると、体の芯からじんわりと温まっていくのが実感できた。
これらの料理は、どれも華美ではない。用いられている素材も、この土地で普通に手に入るごく身近なものばかりだ。しかし、だからこそそこにはごまかしの効かない本物の美味しさがあり、日々の暮らしに根ざした食文化の奥深さがぎゅっと詰まっている。僕はもっと深く、この味の根源に触れてみたいと強く願うようになった。レストランの洗練された料理ではなく、普通の家庭の台所で、ありのままにお母さんやおばあちゃんが作る、素朴なジロカストラの味に。
家庭のキッチンへ、時を超える料理体験の扉を叩く

その願いを滞在中のゲストハウスの主人に打ち明けると、驚くほどあっさりと叶うことになった。「それなら、僕の姉の家で料理を習ってみたらどうかな。彼女は料理が本当に上手なんだよ」。アルバニア人のホスピタリティには、いつも感心させられる。
こうして僕はジロカストラの家族のもとを訪れ、一緒に料理を作るという貴重な経験をすることとなった。近年では、僕のような旅行者向けに、こういった家庭料理体験を提供する家庭や小規模なツアー会社が増えているようだ。インターネットで調べれば、いくつかのプランが見つかるはずだ。料金は内容によって異なるが、僕が参加した半日体験なら、1人あたり30ユーロから50ユーロほどが相場だろう。準備から調理、食事まで含めると、およそ3~4時間かかる。それは単なる料理教室以上に、文化交流の場としても価値があると思う。
約束の日、僕は少し緊張しつつ大きな期待を抱き、指定された家へ向かった。旧市街の奥まった静かな路地裏にその家はあった。石造りの壁に鮮やかな花が咲くプランターが飾られた、愛らしい家だ。ドアをノックすると、笑顔の素敵な女性、エレナさんが出迎えてくれた。彼女はゲストハウスの主人の姉だった。
「Përshëndetje! よく来てくれたわね、さあどうぞ」。
一歩家に入ると、ハーブやスパイスの香りと、何かを煮込む甘い香りが入り混じった温かな空気に包まれた。リビングを通り抜けて案内されたキッチンは、最新の設備が揃っているわけではないものの、使い込まれた木製の調理台や壁に掛けられた銅鍋のひとつひとつから、この家の食の歴史が感じられた。窓からは明るい日差しが差し込み、庭で育つミントやローズマリーが風に揺れているのが見えた。ここが今日の舞台だった。
おばあちゃん直伝、Qifqi作りの秘訣
この日僕が教わるのは、忘れられない味のQifqiと、もう一品、野菜を使った煮込み料理だった。隣にはエレナさんの母親であるおばあちゃんもいて、優しい笑顔で僕を見守っている。今日の指導者はこの二人だ。
「Qifqiはね、ジロカストラの魂とも言える料理よ」とエレナさんは話す。「昔は特別な鉄鍋でひとつずつ丁寧に焼いていたけれど、今は揚げる家庭が多いわ。でも大切なのは、材料のシンプルさと愛情を込めること」。
テーブルには大きなボウルに炊きたての米、平皿に新鮮なミントの葉、地鶏の卵、塩と黒胡椒が用意されていた。特別なものは何もない。特別な調理器具も必要なく、エプロンさえ貸してもらえればすぐに始められる気軽さが嬉しい。動きやすい服装で来たのは正解だった。軽いカメラも持ってきたが、まずは調理に集中しようと思う。
作業はミントの葉を細かく刻むところから始まった。トントン、トントンとリズムよく包丁を動かすおばあちゃんの手つきは見事だ。僕も真似してみるがなかなか同じようにはいかない。「もっと細かくね。香りが立つように」とおばあちゃんが身ぶり手ぶりで教えてくれる。言葉はあまり通じないが、その目線と動作で何を伝えたいのか自然と理解できた。
次に温かい米の入ったボウルに刻んだミント、溶き卵、塩、胡椒を加えて混ぜていく。「ここでのポイントは、米粒を潰さずにさっくり混ぜること」とエレナさんが助言する。「卵を混ぜすぎると固くなってしまうので気をつけて」。彼女たちの手さばきはまるで音楽のようだ。強過ぎず弱過ぎず、完璧なリズムで材料が馴染んでいく。
混ざった生地を今度は手で小さなボール状に丸める。手のひらに少量のオリーブオイルを塗るのがくっつかないコツらしい。一つ一つ、サイズが均等になるよう丁寧にこの単純な動作に妙に心が和む。僕が作った不格好なボールを見て、エレナさんとおばあちゃんが笑い合い、その笑い声がキッチンの温かい空気に溶け込む。
すべて丸め終わったら、いよいよ揚げる段階だ。鍋にたっぷり注がれたオリーブオイルが熱せられ、パチパチと音を立て始める。エレナさんが菜箸の先を油に浸して温度を確かめる。「これくらいね」と言うと、丸めた生地をそっと油の中に滑らせた。ジュワッという心地よい音と共にQifqiは黄金色に変わっていく。キッチン中に、米とミントとオイルが混じり合った食欲をそそる香りが満ちた。
きつね色に揚がったQifqiを網杓子ですくいあげ、油を切る。完璧な球体。完璧な色合い。僕も一つ揚げさせてもらった。熱い油に少し緊張したが、エレナさんの「大丈夫よ」の声に励まされ、そっと鍋へ投入。自分の手で作ったQifqiが美味しく揚がっていく様子は感動的だった。
笑顔と語らいが彩る、食卓のひととき
Qifqiともう一品の野菜煮込み「Fergesë(フェルゲス)」が仕上がる頃には、僕とエレナさん、おばあちゃんはすっかり打ち解けていた。言葉の壁は笑顔やジェスチャー、そして料理という共通言語が容易に乗り越えてくれた。
家のダイニングテーブルに出来たての料理が並べられる。揚げたてのQifqi、トマトとパプリカ、フェタチーズの熱々のFergesë、自家製パン、庭で採れたオリーブの塩漬け、そして地元の白ワインが並ぶ。豪華ではないかもしれないが、豊かで温かい食卓だった。
「さあ、たくさん食べてね。あなたが作ったQifqiよ」。
エレナさんに促され、揚げたてのQifqiをひとつ手に取った。熱々で表面はカリッとしている。一口かじるとサクッという軽やかな音とともに、ミントの爽やかな香りが口の中に広がった。中は驚くほどふんわりとしていて、米の粒がしっかり立っている。自分で作ったという事実が何よりのスパイスになっていた。これはレストランで食べたどのQifqiよりも美味しかった。
食事をしながら、たくさんの話を交わした。エレナさんは子供の頃の話や共産主義時代のこの街のことを語り、おばあちゃんは母親から教わった料理の秘伝を話してくれた。僕は日本のことやこれまで旅してきた場所の話をした。エレナさんは英語が堪能で、通訳を通しおばあちゃんとも会話ができた。
「昔はもっと大変だったのよ」とおばあちゃんは言う。「食材も限られていたし、今のように何でも手に入るわけじゃなかった。でもだからこそ、一つのパンや一杯のスープを家族で分け合う喜びがあった。料理は家族の絆をつなぐ大切なものだったの」。
その言葉が胸に深く響いた。今味わっている美味しさは、単なる調味や調理法の賜物ではない。食材が育ったジロカストラの土地、長年かけて洗練されたレシピ、そして何より家族を想う作り手の深い愛情。すべてが重なってこの一皿は生まれているのだ。
ワインを飲み、パンをちぎってFergesëのソースに浸し、Qifqiを頬張りながら笑い合う。それはこれまで経験したどんな豪華な食事以上に心に残る豊かな時間だった。旅人がほんのひととき、現地の家族の一員になれたような、不思議な感覚。この温かな記憶こそ、僕がジロカストラで見つけた何よりの宝物だったのかもしれない。
ジロカストラ料理体験、旅の準備と心得
僕が体験した素晴らしい時間は、ジロカストラを訪れるすべての人に開かれている。もしこの石の街で、単なる観光客に終わりたくないなら、ぜひ家庭料理体験の世界に一歩踏み出してほしい。そのためのちょっとしたアドバイスをここにまとめておこう。
まずは予約について。僕の場合、ゲストハウスの紹介で運良く参加できたが、確実に体験したいなら事前予約がベストだ。特に夏の観光シーズンは早めの行動が肝心だ。「Gjirokastra Cooking Class」や「Local Cooking Experience」といったキーワードで検索すれば、現地のツアー会社や個人のホストが提供するプログラムがいくつか見つかるはず。レビューを参考に、自分に合うスタイルを選ぶといいだろう。多くのホストはウェブサイトやメッセージアプリを通じて直接連絡が取れる。
次に料金と所要時間だが、先に述べたように、半日程度の体験で1人あたり30ユーロから50ユーロが目安だ。この料金には、食材費やレッスン料、そして実際に作った料理をみんなで味わう食事代が含まれている。ワインやラキ(アルバニア特産の蒸留酒)が振る舞われることも多い。そう考えれば、レストランでの食事と比べて遜色なく、むしろコストパフォーマンスは高いだろう。開催時間は午後から始まって夕食をともにする場合が多いが、午前中のコースもあるので、旅程に応じて選べるのが魅力だ。
服装については、とにかく動きやすくて多少汚れても気にならないものを選ぼう。高級な服を用意する必要はまったくない。調理するので、足元は滑りにくい靴が安全だ。持ち物は基本的に不要で、エプロンや調理器具はすべて揃っている。ただし、体験の様子を写真や動画で残したい場合は、カメラやスマートフォンを忘れずに持参しよう。撮影は調理の妨げにならないようにし、ホストファミリーのプライバシーにも配慮することが大切だ。
最後に言語の心配について。多くのホストは観光客対応に慣れており、ほとんどの場合英語でコミュニケーションが取れるため、アルバニア語が話せなくても問題ない。それでも、もし少しでも距離を縮めたいなら、簡単な挨拶をいくつか覚えていくことをおすすめする。「Përshëndetje(ペルシェンデティエ/こんにちは)」「Faleminderit(ファレミンデリット/ありがとう)」「Shumë e shijshme(シュメ・エ・シイシュメ/とても美味しいです)」といった言葉が、相手の心を開き、より温かい交流につながることを僕は何度も実感している。なお、食材にアレルギーがある場合は、予約時に必ず忘れずに伝え、安全に楽しむための重要な準備を怠らないようにしよう。
石畳の向こうに、まだ見ぬ味を探して

エレナさんの家を後にしたとき、夜空には満月が輝いていた。月明かりに照らされた石畳は、昼間の鈍い銀色とは異なり、青白く優しい光を放っていた。満たされたお腹とともに、言葉に尽くせないほどの温かな感情が心を包んでいた。
この料理体験で僕が得たものは、Qifqiのレシピだけではなかった。それはジロカストラの石造りの家々の中で今なお息づく、人々の暮らしのぬくもりそのものだった。おばあちゃんの深い皺に刻まれた優しい手の温もり、エレナさんの澄んだ笑い声、そして食卓を囲む家族の穏やかな空気。こうしたものは、どんなガイドブックにも載っていない、この街の最も美しい姿だった。
旅というのは、ただ風景を眺めるだけではない。その土地の空気を吸い、その地の声音に耳を澄まし、さらにその土地の味覚を、人と触れ合うことで知ることなのだ。ジロカストラの家庭料理には、オスマン帝国時代から紡がれてきた長い歴史と激動の時代を乗り越えた人々の知恵、そして何よりも深い家族への愛情が融合しており、それはまさに「味わう歴史」だった。
もしもあなたがいつか、このアルバニアの石の街を訪れることがあれば、ぜひ思い出してほしい。壮麗な城塞の向こう、迷宮のようなバザールの奥に、ありふれた普通の家庭のキッチンがあることを。そこでは旅行者であるあなたを暖かく迎え入れ、人生で最も美味しい一皿を共に作り出す家族が待っているかもしれない。その一皿が、あなたの旅を忘れがたいものに変え、ジロカストラの石畳を踏みしめるあなた自身の足音を、歴史の響きの一部へと昇華させてくれるはずだ。